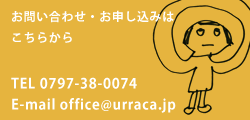石のワーク
先日拾った小石が、どこかしっくりこなかったので、早起きをして山に登ってみました。
代わりの石を探そうと思ったのです。
手元にある小石は、白色ですが、ところどころ赤茶っぽいところがあり、何本もの傷が入っています。
小ぶりの可愛らしい石なのですが、少しいびつな形をしていて、指で触ると、段差というか、でっぱりが感じられます。
そのあたり、なんとなく不器用で、頑固な印象も受けます。
でもなにかちょっと違うような気がする。
その人の顔を思い浮かべては、石を眺めたり触れたりして、「感じ」を確かめてみます。
やっぱりこれでいいのかな。
でも、どこか収まらない。
もっとぴったりした石があるんじゃないかな。
なんてことを思いながら、山道を散歩します。
六甲山から流れる川ぞいの道で、山に入るとちょっとした渓谷のようになっています。
沢には猪の親子がいました。
母猪が見守る中で、ウリ坊が二匹、水辺の土を掘り返しています。
木の根っこや虫の幼虫などを食べているみたいです。
先日、同じあたりで見かけた迷子のウリ坊が、無事に母親に会えたのかもしれません。
ウリ坊に特徴的な縞模様はもう消えかかっていて、なかなか立派な子供猪です。
野生動物の子は、過酷な環境でもずいぶんたくましく成長しますね。
毎年見ていると、もう少ししたら、自然に親離れ子離れして自立していくようです。
親子関係をこじらせる猪があまりいなさそうなのは(たぶんいないと思う)、言葉や観念に縛られていないからでしょう。
石の話でした。
何万年前の遺跡から、人の顔に似た石がたくさん発見されることがあるといいます。
きっとずいぶん昔から、「この石は死んだじいちゃんに似てるぞ」とか「あの娘の顔みたい」といったふうに人は石に誰かの面影を見てきたのだと思います。
墓石は、死者が土の下からよみがえってこないように、「重し」として乗せたのだ、という説を聞いたことがあります。
人が、動物とは違った意味で「死」を恐れるようになったことと、石でこの世とあの世が区分されたのは同じことです。
日本神話では、死んだイザナミから逃げ出したイザナギが、現世と死者の国の境界である黄泉比良坂(よもつひらさか)に岩を置いて塞いだことが、人の「死」の始まりだと説明されています。
そういえば「亡くした女を想う」と書くと「妄想」という字になります。すでに失われた対象、目の前に「ない」何かをイメージする能力は、人のマインドが「今ここ」を離れて「いつか・どこか」に飛躍することを可能にしました。
だからこそ、神様や神話を信じ、国家のような想像の共同体を立ち上げ、ピラミッドや城や橋といった巨大な建築物(あるいは船やロケットやミサイルなど)を作ることができるようになったのです。一方で、人のマインドが進化させたこの妄想能力は、「すでにない」過去へのとらわれや、「まだない」将来の不安も生み出しました。
石は、人々の記憶を刻み込むためにも用いられてきました。もう終わってしまった、あるいは失われてしまったけれども、忘れてはいけないと感じられる出来事の記憶を保存するために、石碑が残されます。
ネイティブ・アメリカンの世界でも、石は記憶や知恵をもつ存在として捉えられてきました。「石のひとたち(インヤン)」とあたかも人格(神格)をもっているかのように表現されます。
といったようなことをぼんやりと考えながら(これも人の妄想能力ですね)、石を拾ったり、放り投げたりして歩きました。
いつか拾って、今は箱庭の棚にこっそりと置いてあるいくつかの石のことも思い出します。
考えてみれば、あの石のひとたちだって、すっかりしっくりくるというわけでもなかったようです。
石を手にとってみるたびに、「なぜ」とか「やっぱりわからない」といった感じがよみがえってくる。石を通して、「ない」という穴の輪郭が、はっきりする。そういうかたちで、記憶や感覚を呼び起こすための装置だと考えた方がよさそうです。
滝つぼまで歩いて少しのあいだそこで過ごしたあたりで、やっぱり最初に拾った小石でいいかもしれない、と思えてきました。
どこか居心地のよさそうなところを見つけて、しばらく置いておくことにします。