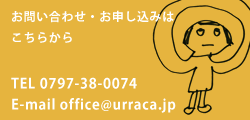令和4年版(第5回)公認心理師試験出題基準・ブループリントと過去問
自分が受験するわけではないのですが、周りに何人か受ける人がいて尋ねられることがあるので、まとめておきます。
公認心理師試験過去問一覧
- 第1回公認心理師試験(平成30年12月16日実施分)午前問題 (PDF:1.21MB)
- 第1回公認心理師試験(平成30年12月16日実施分)午後問題 (PDF:1.20MB)
- 第1回公認心理師試験(平成30年9月9日実施分)午前問題 (PDF:1.21MB)
- 第1回公認心理師試験(平成30年9月9日実施分)午後問題 (PDF:1.20MB)
ブループリント(公認心理師試験設計表)
| 到 達 目 | 標(目安) | 出題割合 | |
| ① | 公認心理師としての職責の自覚 | 約9% | |
| ② | 問題解決能力と生涯学習 | ||
| ③ | 多職種連携・地域連携 | ||
| ④ | 心理学・臨床心理学の全体像 | 約3% | |
| ⑤ | 心理学における研究 | 約2% | |
| ⑥ | 心理学に関する実験 | 約2% | |
| ⑦ | 知覚及び認知 | 約2% | |
| ⑧ | 学習及び言語 | 約2% | |
| ⑨ | 感情及び人格 | 約2% | |
| ⑩ | 脳・神経の働き | 約2% | |
| ⑪ | 社会及び集団に関する心理学 | 約2% | |
| ⑫ | 発達 | 約5% | |
| ⑬ | 障害者(児)の心理学 | 約3% | |
| ⑭ | 心理状態の観察及び結果の分析 | 約8% | |
| ⑮ | 心理に関する支援(相談、助言、指導その他の援助) | 約6% | |
| ⑯ | 健康・医療に関する心理学 | 約9% | |
| ⑰ | 福祉に関する心理学 | 約9% | |
| ⑱ | 教育に関する心理学 | 約9% | |
| ⑲ | 司法・犯罪に関する心理学 | 約5% | |
| ⑳ | 産業・組織に関する心理学 | 約5% | |
| ㉑ | 人体の構造と機能及び疾病 | 約4% | |
| ㉒ | 精神疾患とその治療 | 約5% | |
| ㉓ | 公認心理師に関係する制度 | 約6% | |
| ㉔ | その他(心の健康教育に関する事項等) | 約2% |
公認心理師試験 出題基準
なんだか表が崩れてますが、まあいいや。
そのうち、余力があればキーワードのそれぞれについて解説をしてみるかもしれません。いや、しなさそう。受験する皆さん、がんばってください。
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 1 公認心理師としての職責の自覚 | (1)公認心理師の役割 | |
| (2)公認心理師の法的義務 及び倫理 | ||
| (3)心理に関する支援を要する者(以下「要支援者」という。)等の安全の確保と要支援者の視点 | ||
| (4)情報の適切な取扱い | ||
| (5)保健医療、福祉、教育その他の分野における公認心理師の具体的な業務 | ||
| 2 問題解決能 力と生涯学習 | (1)自己課題発見と解決能力 | |
| (2)生涯学習への準備 | ||
| 3 多職種連携・地域連携 | 多職種連携・地域連携の意義及びチームにおける公認心理師の役割 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 4 心理学・臨床心理学の全体像 | (1)心理学・臨床心理学の成り立ち | |
| (2)人の心の基本的な仕組 みとその働き | ||
| 5 心理学における研究 | (1)心理学における実証的研究法 | |
| (2)心理学で用いられる統 計手法 | ||
| (3)統計に関する基礎知識 | ||
| 6 心理学に関する実験 | (1)実験計画の立案 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 6 心理学に関する実験(続 き) | (2)実験データの収集とデータ処理 | |
| (3)実験結果の解釈と報告書の作成 | ||
| 7 知覚及び認知 | (1)人の感覚・知覚の機序及びその障害 | |
| (2)人の認知・思考の機序及びその障害 | ||
| 8 学習及び言語 | (1)人の行動が変化する過程 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 8 学習及び言語(続き) | (2)言語の習得における機序 | |
| 9 感情及び人格 | (1)感情に関する理論と感情喚起の機序 | |
| (2)感情が行動に及ぼす影 響 | ||
| (3)人格の概念及び形成過 程 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 9 感情及び人格(続き) | (4)人格の類型、特性 | |
| 10 脳・神経の働き | (1)脳神経系の構造と機能 | |
| (2)記憶、感情等の生理学的反応の機序 | ||
| (3)高次脳機能の障害と必要な支援 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 11 社会及び集団に関する心理学 | (1)対人関係並びに集団における人の意識及び行動についての心の過程 | |
| (2)人の態度及び行動 | ||
| (3)家族、集団及び文化が個人に及ぼす影響 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 12 発達 | (1)認知機能の発達及び感情・社会性の発達 | |
| (2)自己と他者の関係の在り方と心理的発達 | ||
| (3)生涯における発達と各発達段階での特徴 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 12 発達(続き) | (4)非定型発達 | |
| (5)高齢者の心理社会的課題と必要な支援 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 13 障害者(児)の心理学 | (1)身体障害、知的障害及び精神障害 | |
| (2)障害者(児)の心理社会的課題と必要な支援 | ||
| 14 心理状態の観察及び結果の分析 | (1)心理的アセスメントに有用な情報(生育歴や家族の状況等)とその把握の手法等 | |
| (2)関与しながらの観察 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 14 心理状態の観察及び結果の分析(続き) | (3)心理検査の種類、成り立ち、特徴、意義及び限界 | |
| (4)心理検査の適用、実施及び結果の解釈 | ||
| (5)生育歴等の情報、行動観察、心理検査の結果等の統合と包括的な解釈 | ||
| (6)適切な記録、報告、振り返り等 | ||
| 15 心理に関する支援(相談、助言、指導その他の援助) | (1)代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義及び適応 | |
| (2)訪問による支援や地域支援の意義 | ||
| (3)要支援者の特性や状況に応じた支援方法の選択、調整 | ||
| (4)良好な人間関係構築のためのコミュニケーション |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 15 心理に関する支援(相談、助言、指導その他の援助) (続き) | (5)心理療法及びカウンセリングの適用の限界 | |
| (6)要支援者等のプライバシーへの配慮 | ||
| 16 健康・医療に関する心理 学 | (1)ストレスと心身の疾病との関係 | |
| (2)医療現場における心理社会的課題と必要な支援 | ||
| (3)保健活動における心理的支援 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 16 健康・医療に関する心理学(続き) | (4)災害時等の心理的支援 | |
| 17 福祉に関する心理学 | (1)福祉現場において生じる問題とその背景 | |
| (2)福祉現場における心理社会的課題と必要な支援方法 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 17 福祉に関する心理学(続き) | (3)虐待、認知症に関する必要な支援 | |
| 18 教育に関する心理学 | (1)教育現場において生じる問題とその背景 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 18 教育に関する心理学(続き) | (2)教育現場における心理社会的課題と必要な支援 | |
| 19 司法・犯罪に関する心理学 | (1)犯罪、非行、犯罪被害及び家事事件に関する基本的事項 | |
| (2)司法・犯罪分野における問題に対して必要な心理的支援 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 20 産業・組織に関する心理学 | (1)職場における問題に対して必要な心理的支援 | |
| (2)組織における人の行動 | ||
| 21 人体の構造と機能及び疾病 | (1)心身機能、身体構造及びさまざまな疾病と障害 | |
| (2)心理的支援が必要な主な疾病 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 22 精神疾患とその治療 | (1)代表的な精神疾患の成因、症状、診断法、治療法、経過、本人や家族への支援 | |
| (2)向精神薬をはじめとする薬剤による心身の変化 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 22 精神疾患とその治療(続き) | (2)向精神薬をはじめとする薬剤による心身の変化(続き) | リン作用、依存耐性、賦活症候群等) |
| (3)医療機関への紹介 | ||
| 23 公認心理師に関係する制 度 | (1)保健医療分野に関する法律、制度 | |
| (2)福祉分野に関する法律、制度 |
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 23 公認心理師に関係する制度(続き) | (2)福祉分野に関する法律、制度(続き) | 待防止法> |
| (3)教育分野に関する法律、制度 | ||
| (4)司法・犯罪分野に関する法律、制度 | ||
| 大項目 | 中項目 | 小項目(キーワードの例) |
| 23 公認心理師に関係する制度(続き) | (5)産業・労働分野に関する法律、制度 | |
| 24 その他(心の健康教育に関する事項等) | (1)具体的な体験、支援活動の専門知識及び技術への概念化、理論化、体系化 | |
| (2)実習を通じた要支援者等の情報収集、課題抽出及び整理 | ||
| (3)心の健康に関する知識普及を図るための教育、情報の提供 |
関連記事
前の記事: 複雑性PTSDのカウンセリング・心理療法
次の記事: 心理療法士の性格特性と治療志向性