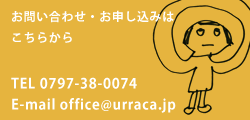チェーホフと言葉の力
映画「ドライブ・マイ・カー」(濱口竜介監督)が、2021年夏に封切られて以降、ロングラン上映を続けています。カウンセラー仲間のあいだでも、「みた?」「よかったよ」などと、話題になっています。
原作は村上春樹の短編小説。同じタイトルの短編が主軸にはなっていますが、映画化にあたって、改変されている部分もけっこうあります。
アントン・チェーホフの戯曲「ワーニャ伯父さん」の使われ方も、原作と大きく異なっているところです。原作でも、主人公である俳優の家福(かふく)が舞台で演じている作品として出てはきますが、さらりと触れられている程度。一方、映画では、俳優たちが稽古を経て上演に至るまでのプロセスが、たっぷりと丁寧に描かれていきます。そして、車のなかでも稽古場でも、繰り返し読みあげられる「ワーニャ伯父さん」のセリフ。それはどこか、奥深く秘められた場所へとわたしたちを運んでいく、呪文のようにも響きます。
映画のなかで、俳優たちが、淡々と「ワーニャ伯父さん」のテキストを読みあげていく場面がありました。かれらは演技をすることを禁じられ、ただセリフを棒読みするよう演出家に求められます。そこで立ちあがってくるのは「言葉」です。演技の前に、まず言葉がある。その言葉の力が、演者の内面を引きずり出してくる瞬間を、演出家は待っているのです(その力を熟知しているから、主人公の家福は演出に徹し、ワーニャを演じようとしません)。
「ワーニャ伯父さん」は、チェーホフの四大戯曲とされるものの一つです。青空文庫にも収載されていて、気軽に手に取ることができます。ただ、読みやすいかというと、戯曲という形式もあり、意見の分かれるところだと思います(小説には読みやすいものも多いのですが)。ストーリーも、とくに心温まるようなものではありません。ロシアの田舎で行き詰った登場人物たちが、なんとかそこから抜け出そうとあがくものの、最後は絶望して幕を閉じます。
登場人物たちはそれぞれに苦悩しています。ワーニャ伯父は、かつて惚れ込み、自らを犠牲にして支えてきた妹婿の「教授」が、まったく中身のない人物であったことに失望し、いらだっています。さらにそれに追い打ちをかけるように、「教授」は、かれらがどうにか維持してきた荘園を売りに出してはどうか、と言いはじめます(それも深い思慮に基づくものではなく、身勝手な思いつきに過ぎません)。ワーニャの怒りはついに爆発します。「教授」に銃口を向け、自らはモルヒネで命を絶とうとします。しかし、そのどちらも果たされることはなく、彼は絶望を抱えて、元の暮らしに戻っていきます。
彼の姪であるソーニャは、まだ若い娘なのですが、戯曲の最後、嘆き悲しむ伯父を包み込むように慰め、「生きていきましょうね」とやさしく励まします。
ワーニャ:(ソーニャの髪の毛を撫でながら)ソーニャ、わたしはつらい。わたしのこのつらさがわかってくれたらなあ!
ソーニャ:でも、仕方がないわ、生きていかなければ! (間)ね、ワーニャ伯父さん、生きていきましょうよ。長い、はてしないその日その日を、いつ明けるとも知れない夜また夜を、じっと生き通していきましょうね。運命がわたしたちにくだす試みを、辛抱づよく、じっとこらえて行きましょうね。今のうちも、やがて年をとってからも、片時も休まずに、人のために働きましょうね。そして、やがてその時が来たら、素直に死んで行きましょうね。あの世へ行ったら、どんなに私たちが苦しかったか、どんなに涙を流したか、どんなにつらい一生を送って来たか、それを残らず申上げましょうね。すると神さまは、まあ気の毒に、と思ってくださる。その時こそ伯父さん、ねえ伯父さん、あなたにも私にも、明るい、すばらしい、なんとも言えない生活がひらけて、まあ嬉しい! と、思わず声をあげるのよ。そして現在の不仕合せな暮しを、なつかしく、ほほえましく振返って、私たち――ほっと息がつけるんだわ。わたし、ほんとにそう思うの、伯父さん。心底から、燃えるように、焼けつくように、私そう思うの。……(伯父の前に膝をついて頭を相手の両手にあずけながら、精根つきた声で)ほっと息がつけるんだわ!
ソーニャ自身もまた、思いを寄せる男性に愛されないという苦悩を抱えています。伯父を慰めながら、ソーニャは、いつか神さまが、自分たちのことを「まあ、気の毒に」と思ってくださるのだと言います。そうすればわたしたちはやっと、ほっと息がつけるのだ、と。ソーニャの口調はだんだん熱を帯び、夢見るように語り続けます。
ソーニャ: ほっと息がつけるんだわ! その時、わたしたちの耳には、神さまの御使(みつかい)たちの声がひびいて、空一面きらきらしたダイヤモンドでいっぱいになる。そして私たちの見ている前で、この世の中の悪いものがみんな、私たちの悩みも、苦しみも、残らずみんな――世界じゅうに満ちひろがる神さまの大きなお慈悲のなかに、呑(の)みこまれてしまうの。そこでやっと、私たちの生活は、まるでお母さまがやさしく撫(な)でてくださるような、静かな、うっとりするような、ほんとに楽しいものになるのだわ。私そう思うの、どうしてもそう思うの。……(ハンカチで伯父の涙を拭いてやる)お気の毒なワーニャ伯父さん、いけないわ、泣いてらっしゃるのね。……(涙声で)あなたは一生涯、嬉しいことも楽しいことも、ついぞ知らずにいらしたのねえ。でも、もう少しよ、ワーニャ伯父さん、もう暫くの辛抱よ。……やがて、息がつけるんだわ。……(伯父を抱く)ほっと息がつけるんだわ!
言葉が人を抱くということがあるのだと、しみじみと実感させられます。わたしたちに、19世紀末のロシアを生きた人々の信仰を共有することはできません。でもこれらの言葉から、ソーニャのやさしさや伯父へのいたわりは、伝わってきます。「空一面のきらきらしたダイアモンド」は、チェーホフからの言葉の贈りものなのでしょう。慈悲深い神さまは「あの世」ではなく、ソーニャが語り掛けるこの瞬間、この言葉のなかに、立ち現れるのです。
チェーホフは大げさなテーマや力強いストーリーを嫌い、人のこころの奥底をじっとのぞきこみむようにして、こまやかに言葉を織りあげ続けました。
濱口竜介監督もまた、言葉の力を信じている人なのだと思います。映画「ドライブ・マイ・カー」では、長く苦しい主人公の旅路のあと、このセリフがスクリーンに映し出されます。そのことで、より一層、映画の世界が深く心に響くのです。言葉は、言葉にならないものをそぎ落とし、意味を断定してしまう働きをします。人をしばり、呪いをかけることすらあります。しかし、丁寧につむがれた言葉は、人の体験を包み込み、熟成させていく容器のような働きもします。カウンセラーとして、人のこころに丁寧に触れ、大切に言葉を使っていきたい。よい作品に触れると、あらためてそうした思いが胸に広がります。(A)
アントン・チェーホフ、神西清訳「ワーニャ伯父さん」『かもめ・ワーニャ伯父さん』新潮文庫、青空文庫、https://www.aozora.gr.jp/cards/001155/files/51862_41345.htm