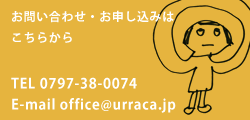カウンセラーの選び方
*この記事は「神戸市・兵庫県であなたに適したカウンセリング・相談先を探すには?」から一部を抜粋し、加筆したものです。
自分の悩みや問題を相談するのに適しているのは、民間の開業カウンセリングルームだろうということになったとします。
「カウンセラーの探し方」にも書いたように、信頼できる人に聞いたり、インターネットなどで探した後は、ご自分で選ばなくてはいけません。カウンセリングルームに電話やメールでより詳しいことを問い合せる場合もあるでしょう。
どんなことに気をつけて選べばいいかを少しまとめてみます。
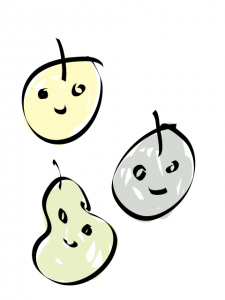
Contents
カウンセラーの専門や臨床経験
ホームページに、カウンセラーのプロフィールが書いてあれば、それを参考にしてください。電話やメールで、「カウンセラーの専門は何か? どんな領域の経験があるか」を尋ねてもいいでしょう。
2015年に「公認心理師法案」が可決され、心理職の国家資格が誕生しました。
2018年には第1回公認心理師試験が実施され、私たちも受験しました(なんとか合格をいただいてます)。
ですので、臨床心理士や産業カウンセラーといった資格が、カウンセラーがどのようなことを勉強してきたかというひとつの目安になります。カウンセリングスクールで数週間講座を受ければ取得できる「資格」から、大学や大学院で何年かまなばなければならないもの、あるいは学会での発表や個人分析、スーパーヴァイズなどの厳しいトレーニングが義務づけられているものまでさまざまです。
*2023年現在の日本では、「臨床心理士と公認心理師の両者の資格を持っている人」が、資格という点では、まず望ましいと考えられます。けれども資格というのは「その分野に関してある程度の知識をもっているよ」という証明なので、それだけで決めてしまうのも問題があります。
詳しくは、カウンセラーの「資格」を参照してください。
ただし、信頼できそうな「資格」をもっていたからといって、「あなたにとっていい」カウンセラーだということにはなりません。資格がなくても、あるいは資格を手放しても、優れたカウンセラーはいます。
けれども、なかにはほとんど経験もなく、学んでもいなくて、「カウンセラー」として開業してしまう人もいるので、この点は注意が必要でしょう。
「うつ病を克服しました」→「うつのカウンセラーになりました」
「恋愛問題で苦しんできました」→「その経験を活かして、恋愛カウンセラーをしています」
といった「経歴」をときどき見かけることがあります(いるんですよ、ほんとに)。
個人的な問題や悩みを克服したという経験が、他人の相談を聞く際に役に立たないということはありませんが、大切なのは個別的な体験をある程度普遍的なスキルにつなげるための努力です。
そのためにどんなトレーニングや臨床経験を積んできたかも併せて尋ねてみましょう。
「自分が苦しんだ体験」だけでカウンセラーをしている人は、「要注意」です。
カウンセラーの「専門領域」が何かを知るには、たとえば「所属学会」などを聞いてみるのも方法です。
「認知・行動療法学会」に所属している、あるいは「精神分析学会」だとか「箱庭療法学会」だとか、「ゲシュタルト療法学会」などの会員であれば、それぞれの学派やアプローチを学んできたカウンセラーだろうと考えることができます。
また、論文や著書があれば、読んでみてもいいでしょう。けれど、たくさん本を書いているからカウンセリングの能力が高いというわけではないですし、文章を先に読んでしまうことで、先入観や期待が大きくなりすぎるのもあまりよくないかもしれません。
ホームページやブログに、カウンセラーの経験や考え方、アプローチなどについて記載しているところも多いので、それも参考になるでしょう。
たくさん資格があって、なんとか療法ができます、かんとか療法もできますと、「技法」がずらずらと並んでいるのは、個人的には「どうかな」と思います。どれかひとつをマスターするだけでも、相当長い経験や勉強が必要だからです。
「臨床経験」については、率直にカウンセラーに聞いてみてください。
精神科をはじめとした病院臨床が長い人であれば、うつ病や不安障害、あるいは統合失調症といった精神疾患をもった人との関わってきた経験があるということになります。
精神疾患のある人のカウンセリングは、やはりそれについての知識や経験が必要ですし、ときに精神科や心療内科と適切な連携をもつことだって求められます。
スクールカウンセラーの経験が長い人でしたら、不登校やいじめ、家族関係などの相談にたくさん対応してきたということでしょう。
あんまり質問攻めにするのもどうかと思われるかもしれませんが、あなたにとって大切なことはちゃんと聞いた方がいいでしょう。
「夫婦関係の問題に対応してこられましたか?」「強迫性障害(あるいは摂食障害やパニック障害など)のケースはどれくらい経験しましたか?」といったことを尋ねて、率直に答えてくれるか、誠実に対応してくれるかどうかを確かめてみてください。
カウンセラーの性別や年齢、人柄、相性など
カウンセリングは非常に個人的な体験ですので、カウンセラーの性別や年齢、人柄、相性などを考慮することも大切です。自分が話しやすい相手であるかどうかを判断するため、初回の面接で直接話してみることが望ましいです。
「カウンセラーはどんな人か」「私と合うだろうか」ということは、やはり気になることでしょう。相談内容によっては「異性のカウンセラーには話しにくい」こともあるでしょうし、年齢や印象などが気がかりなこともあるかもしれません。
「女性のカウンセラーがいるから」
「写真や文章を見て、なんとなく合いそうだから」
「電話で話したときの声のトーンが穏やかだった」
といったような印象で選ぶのも、もちろんありです。また、実際に合ってみたときの印象で、カウンセリングを続けるかどうかを決める人も多いかもしれません。
思春期の心理臨床などでは、ときどき「new object(新しい対象)としてのカウンセラー」と言うこともあります。これまで出会ったことのないようなタイプの人物に出会うことが、子どもの成長にとって意味があるというような文脈で語られます。
大人の人にとっても似たところはあるかもしれません。信頼できそうな安心できる人柄で、それでいて、少し意外性もあるようなカウンセラーと出会えると、いい変化が起きやすいでしょう。
「カリスマ的なカウンセラー」なんていう人もときどき見かけますが、個人的な見解としては、「カウンセラーにはカリスマ性なんてあんまりいらないんじゃない?」と思います。「カリスマ・カウンセラー」になったことも、言われたこともないので、実際のところは分かりませんが、むしろ、邪魔になることの方が多いんじゃないでしょうか。
カウンセリングの主体はあくまでクライエント(来談者)です。カウンセラーが「カリスマ」になると、カウンセラーが真ん中に来ることになってしまいかねません。
それに、カウンセリングという営みは、人生の舞台裏です。クライエントは、また日常生活に返っていかなくてはいけません。だから、用が済んだらカウンセラーはぽいと捨てて立ち去ってもらうということも大切なのです。このあたり、カウンセラーとクライエントのもつ関係の独特なところで、とても親密に、プライベートなことを話したり、聴いたりする仲でありつつ、そこには料金という「水臭い」「ドライな」ものも介在していて、時期がくればあっさりと離れるのです(言葉はちょっと悪いですが、「後腐れない」という言い方もできます。余談ですが、「水臭い」と「ドライな」という水分に関する言葉が、どちらも情が薄い、他人行儀だという意味合いをもっているのは、面白いですね)。
もうひとつ大事なポイントとして、カウンセラーは親しい友人や仕事その他での関係のない「他人」であるほうがいいということが挙げられます。カウンセリング以外の日常生活で関わることがあると、プライベートなことを話しにくいですし、現実的な利害関係がカウンセリングに影響を及ぼすこともあるからです。
カウンセリングルームの場所や構造
カウンセリングルームの場所や構造も、カウンセリングを受ける上で重要です。通勤時間や距離、アクセスのしやすさ、プライバシーなどを考慮する必要があります。また、カウンセリングルームの雰囲気や設備も、受けやすさに影響を与える要素となります。
一般的には、自宅からほどほどの距離で、通いやすい場所にあるカウンセリングルームがいいでしょう。人によっては、「あんまり近所だと話しにくい」ということもあるかもしれません。また、「このカウンセラーがいいから」ということで、遠くから通ってきてくださることもあります。長い時間を費やして電車その他の交通機関に乗ってあれこれ想ったり感じたりしながらカウンセリングルームまでやってくるというそのプロセスも、心を見つめるひと時になっているとも言えます。
ときどき、カフェなどのカウンセリングルーム以外の場所でカウンセリングを行っているところがありますが、原則としてはこれはあまり望ましくないと考えています。プライバシーが守られにくいということもありますし、カウンセリングで場所と時間を定めるのは、「自由にして保護された空間」をつくるために重要なことなのです。
相談室の場所や構造については、たとえばクリニックやサロンのように開かれた感じのところがいいのか、ひっそりと目立たないところがいいのか、といったことが選ぶ基準になるでしょうか。
ビルのワンフロアにあって、看板も出ていて、受付もあるカウンセリングルームは、よりオープンで公的な印象を受けるでしょう。マンションの一室に、看板も目立たないようにして開室しているカウンセリングルームは、よりプライベートなカウンセリングを行なっていると感じられるかもしれません。
ホームページに部屋の写真などが掲載されていると、カウンセリングルームの雰囲気が少しわかるでしょう。最初のカウンセリングではなかなか余裕がないかもしれませんが、実際に訪ねたときに、カウンセリングルームの雰囲気を意識してみるのもいいかもしれません。個人開業のカウンセリングルームは、カウンセラーの個性や考え方が反映された場所になっているからです。
ちなみにかささぎ心理相談室は、一般的なマンションの部屋を借りて開室しているので、初めて来られた方が「家みたいですね」「靴を脱ぐんですね」と驚かれることもあります。
自分自身の感覚や好みを大切に
いろいろと挙げてきましたが、実際にカウンセラーと電話で話してみて、あるいは会ってみて、あなたがどう感じるかということがいちばん大切です。
「なんとなくこの人嫌だな」とか「まだよくわからないけど安心できる」といった自分の直感が重要です。
「合わない」と感じるのでしたら、他のカウンセラーに代わるのもありです。
自分の感覚を判断の手掛かりにするときのポイントは、「これは頭が考えてることなのか、私の身体が感じていることなのか」を少し分けてみるということです。
直感は頭ではなく、身体の知恵なので、「からだの声を聞く」ことが重要です。
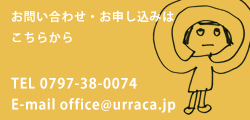
カウンセリングの料金とシステムがニーズに合っているか?
「1回だけの相談」ということもありますが、一般的にはカウンセリングは数回〜15回くらい、あるいは数年にわたって通い続けることになります。
毎週の人もいれば、二週か三週に一度、月に一度、クライエントの希望や状況によって、あるいはカウンセラーの考え方によっても頻度は変わってきます。
そのカウンセラーの料金が、経済的に支払うことのできる額かどうかということが、まず選択の際の基準になってくるでしょう。
料金システムが明確かどうかということもポイントです。「キャンセル料」や「延長料金」については、前もって確認しておくことが必要です。場所によっては、チケット制や前払い制を取っているところもあるようですが、高額な料金を事前に要求するようなところは避けたほうがいいと思います。カウンセリングの後にそのつど支払うのが一般的です。
カウンセリングの料金が高額であれば、それだけ質のいいカウンセリングを受けることができるというわけではありません。先ほども書いたように、料金の相場は、一般的には5000円〜15000円くらいの範囲に入ることが多いですが、カウンセラーの経験やカウンセリングに要する時間や方法によっても異なってきます。
逆に、安ければいいのかと言われると、そうでもないでしょう。カウンセラーがその料金でちゃんとカウンセリングルームを運営して、生活できているかどうかという現実的な枠組みが、カウンセリングのプロセスにも影響を与えると思います。
趣味や片手間でカウンセリングをやられるのも困りますし、あるいは壮大な理念だとか、そのカウンセラーの個人的なニーズ(カリスマ・カウンセラーになりたいとかね)ばかりが前に出るのも問題です。
アメリカの精神科医のハリー・スタック・サリヴァンは、「いちばん信頼のおける治療者は日々の糧のために働く治療者だ」と言いました。
カウンセリングルームへの問い合せと申し込み
多くのカウンセリングルームは、病院などと違って予約制となっています。電話やメールで、最初のコンタクトを取ることが多いでしょう。
まず第一に、相談したい内容や、希望の日時、カウンセラーへの要望などを簡単に伝えます。あなたの悩みや問題に、そのカウンセリングルームが対応できるかどうかということも確かめましょう。
続いて、料金や時間、事前に用意するものがあるか、といったことも確認しておきます。
こういったやりとりのときに、しっかりと誠実に対応してくれるかどうか、カウンセラーの雰囲気はどうか、といったことを意識しておくといいと思います。
対応に疑問が残る、どうも合わないと感じるという場合には、「やっぱりもう少し考えてからにします」と断ったっていいのです。
かささぎ心理相談室では、事前に「相談申し込み票」をお送りして、相談内容やこれまでの経緯、どうなりたいかといったことを書いてきていただくようにしています。
クライエントにとっては、相談内容を自分で少し整理する機会になると思いますし、カウンセラーも必要なことをもらさず知っておくことができるからです。
カウンセリングに申し込むというアクションを起こしたことそのものが、クライエント自身が問題解決に向かって一歩踏み出したということでもあります。
カウンセリング初回の面接のとき
予約した時間の少し前に、カウンセリングルームを訪ねます。遅れそうなら、電話などで連絡しておいたほうがいいでしょう(遅れると、それだけ相談する時間が短くなることがあります)。
カウンセリングが始まったら、いま困っていることや、悩んでいること、問題について話してください。
うまくまとめなくても、感じたままに話せばいいのです。
どんなふうに話せばいいか、うまく話せるかと迷っている方は、
も読んでみてください。
ひととおり話した後は、カウンセラーの意見を尋ねてみましょう。今、あなたが話した困りごとを、カウンセラーはどのようにとらえたのか、カウンセリングで手助けすることができそうなのか、だとしたらどんなふうに取り組んでいくといいと考えているのか。
こういったカウンセラーの「見立て」を聞いて、料金や頻度について話し合い、納得すれば、カウンセリングを継続するということになります。
もちろん、「今日はとりあえず相談したかっただけなので、今後どうするかは持ち帰って考えたい」ということで終わってもかまわないのです。ここで「次回の予約」を無理に取ろうとするカウンセラーは、あまりおすすめしません。
カウンセラーと相性が良くない、あるいはカウンセリングに疑問を感じるとき
何度かカウンセリングに通ってみたけれど、「どうもこのカウンセラーとは相性が良くない」とか「このままここでカウンセリングを続けていて改善するんだろうかと疑問」を感じることもあるかもしれません。
たとえば、
「やはり女性の(あるいは男性の)カウンセラーのほうが話しやすい」
「自分の悩みや症状には、医療機関のほうが適しているのかもしれない」
「経済的に難しいので、料金の安いところを探したい」
といった希望があれば、それを率直に伝えてください。
必要に応じて、別のカウンセラーや病院を紹介してくれると思います。
あるいは、今のカウンセラーとそうしたことを話し合うこと自体に意味があるということも考えられます。主治医がいれば、医師としての意見を聞いてみることもできるでしょう。
それでは、あなたにとって最も適切で相性のいいカウンセラーと出会えますよう、私たちもお祈りしています。
最後に、かささぎ心理相談室のご案内もご一読いただけたら嬉しいです。